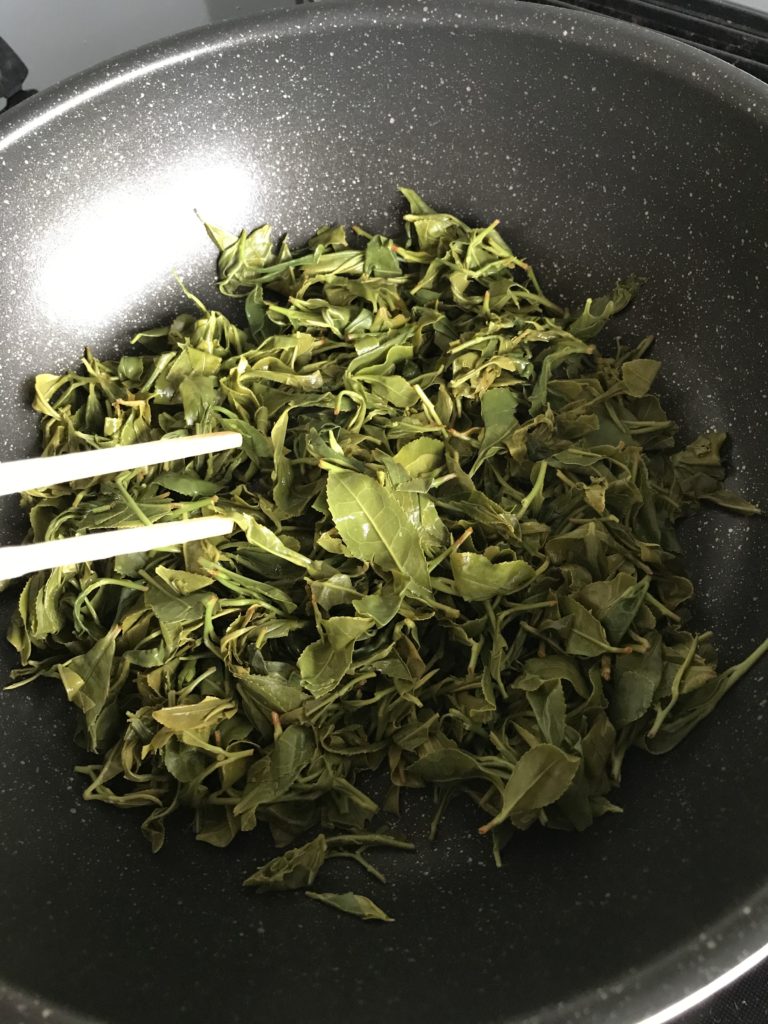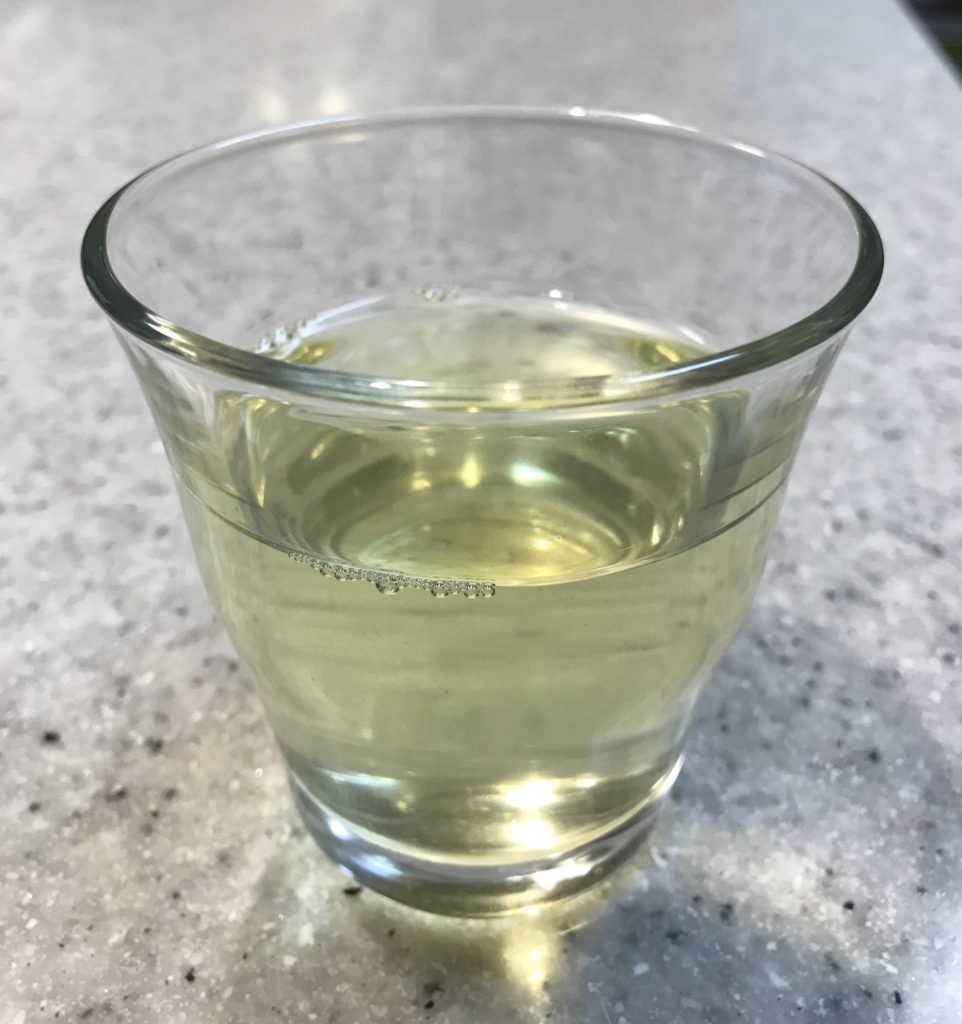新成人の皆様、おめでとうございます。

晴れやかなこの日を迎えられた姿をテレビなどで目にすると、大寒波と緊急事態宣言に重くなっていた心に、輝くような笑顔が染み渡ります。
成人式が中止や延期となり、昨年とは様子が違う成人の日となりました。
今年の受験生についてもそうですが、「かわいそうに…」という声をよく耳にします。
その気持ちは優しさからくるもので、私たちもついそんな風に言ってしまいがちです。
でも、それは決して不運なことではありません。
置かれた状況、環境で最大限の力を発揮することに注力し、この試練を乗り越えてください。
マイナスな条件をプラスに変えることができれば、きっとその後の人生にも大きな力になるはずです。
どの部分にフォーカスして物事をみるか。
それによって、結果までもが違ってくるのだと思います。
日常はその繰り返しなのです。
私たち大人もみんな、がんばりましょう!






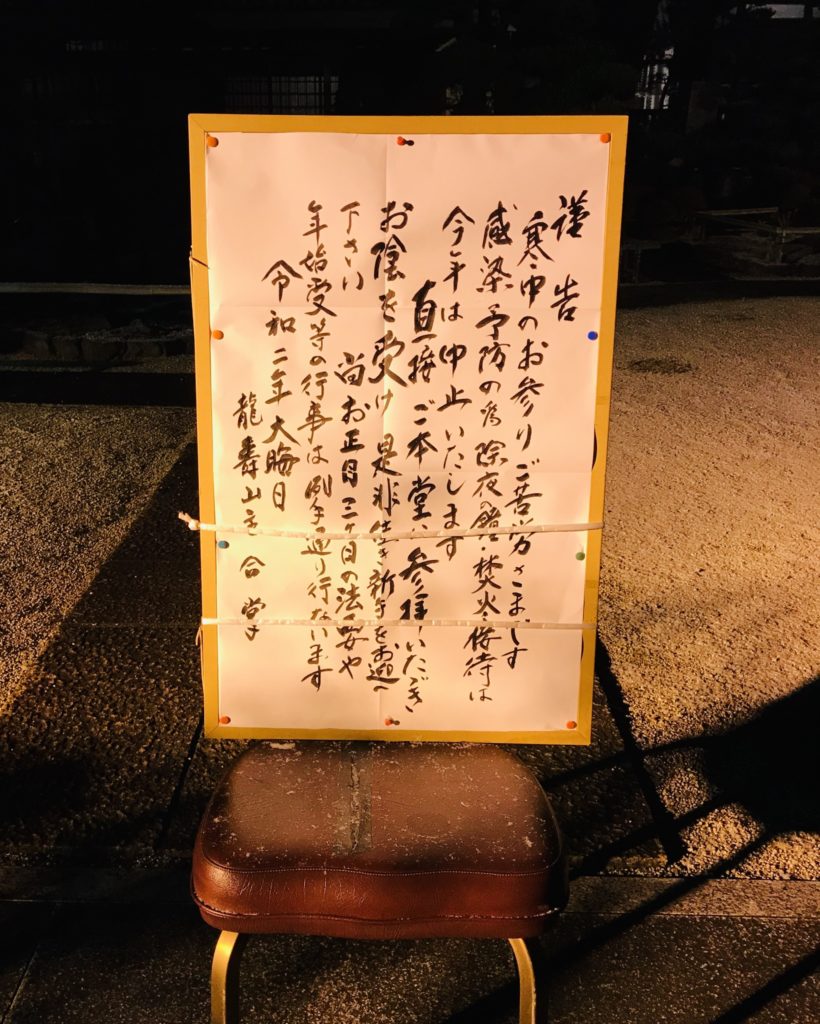




 この二枚の写真は孫の佑美(中2)が撮ったものです。
この二枚の写真は孫の佑美(中2)が撮ったものです。